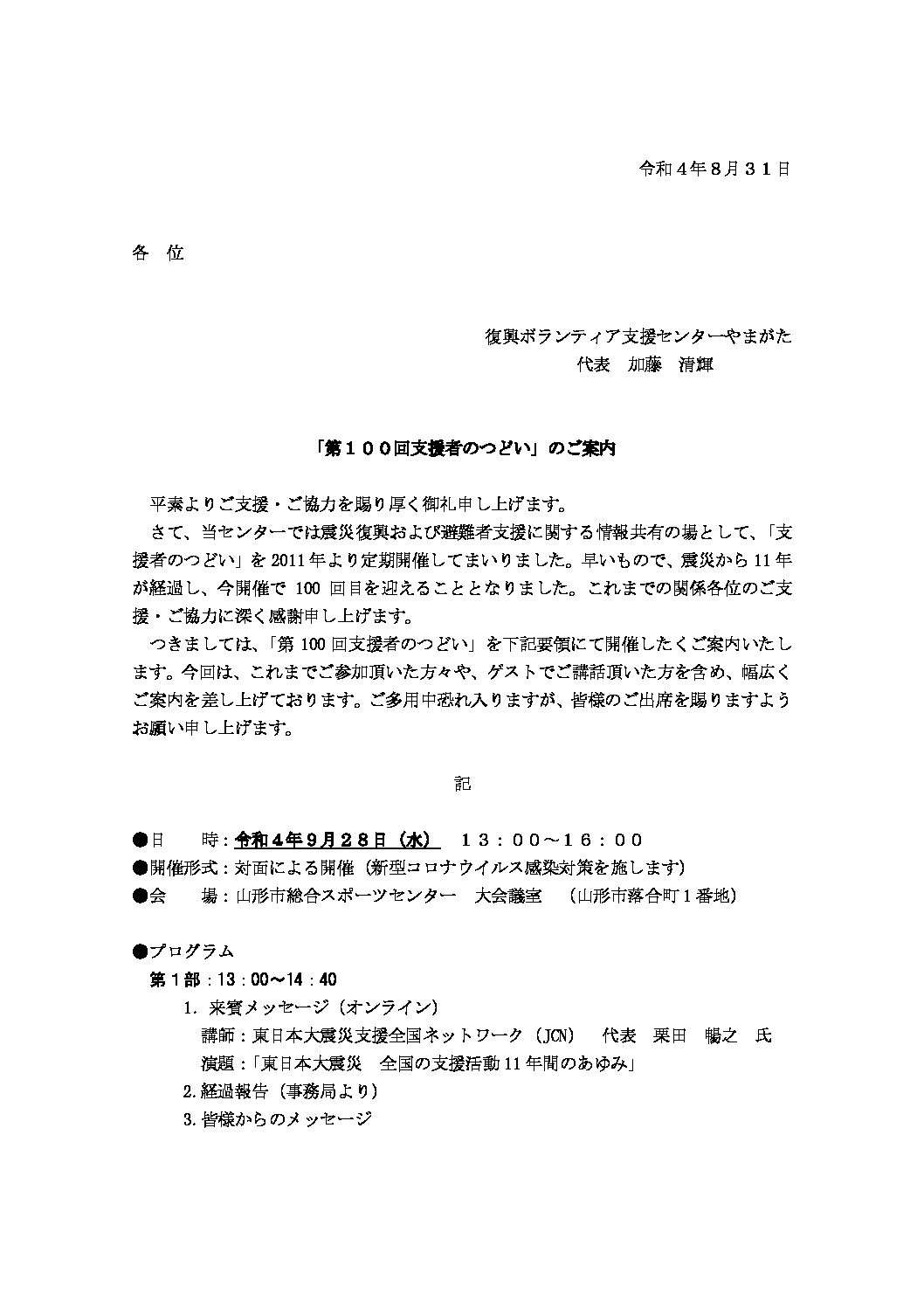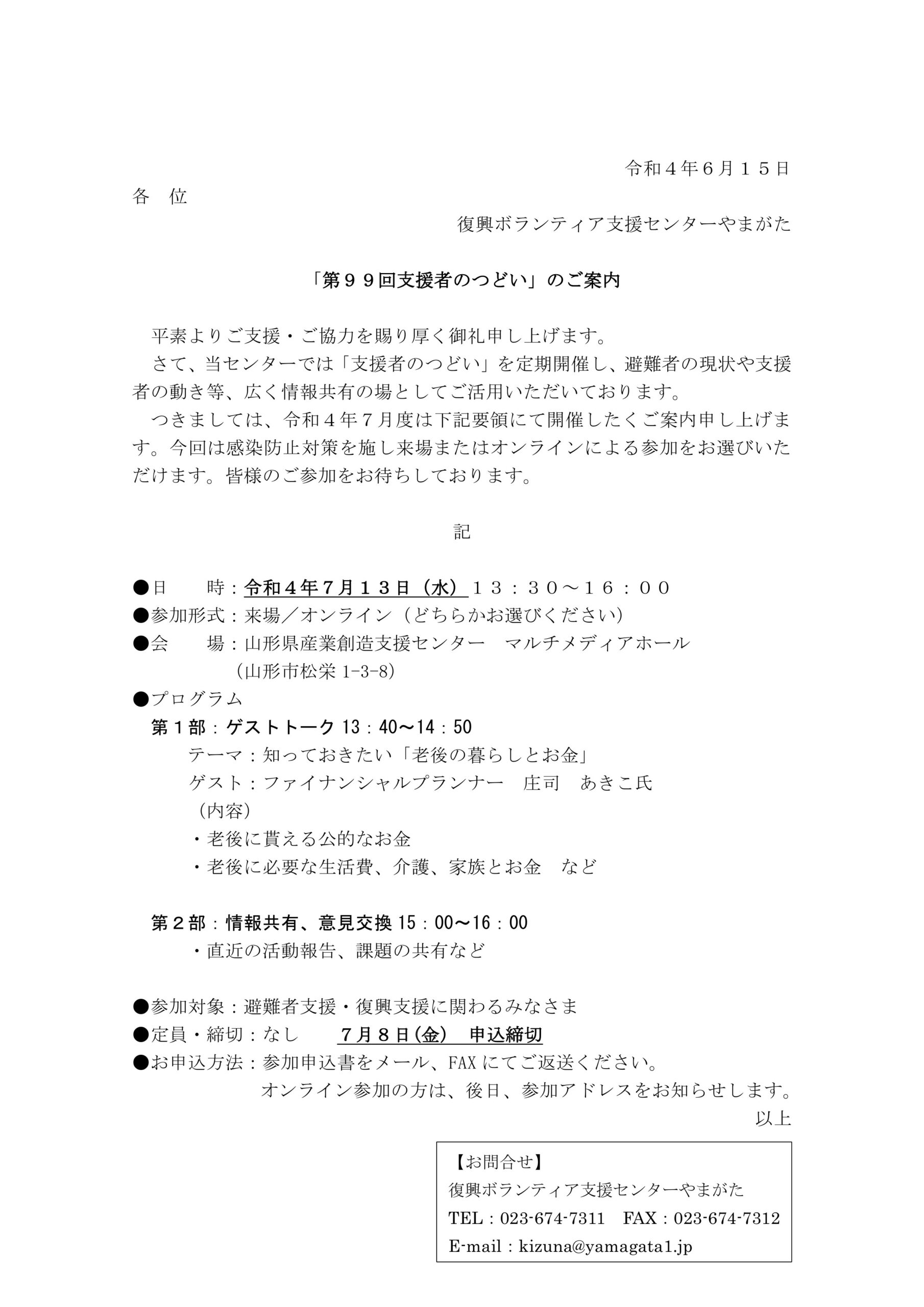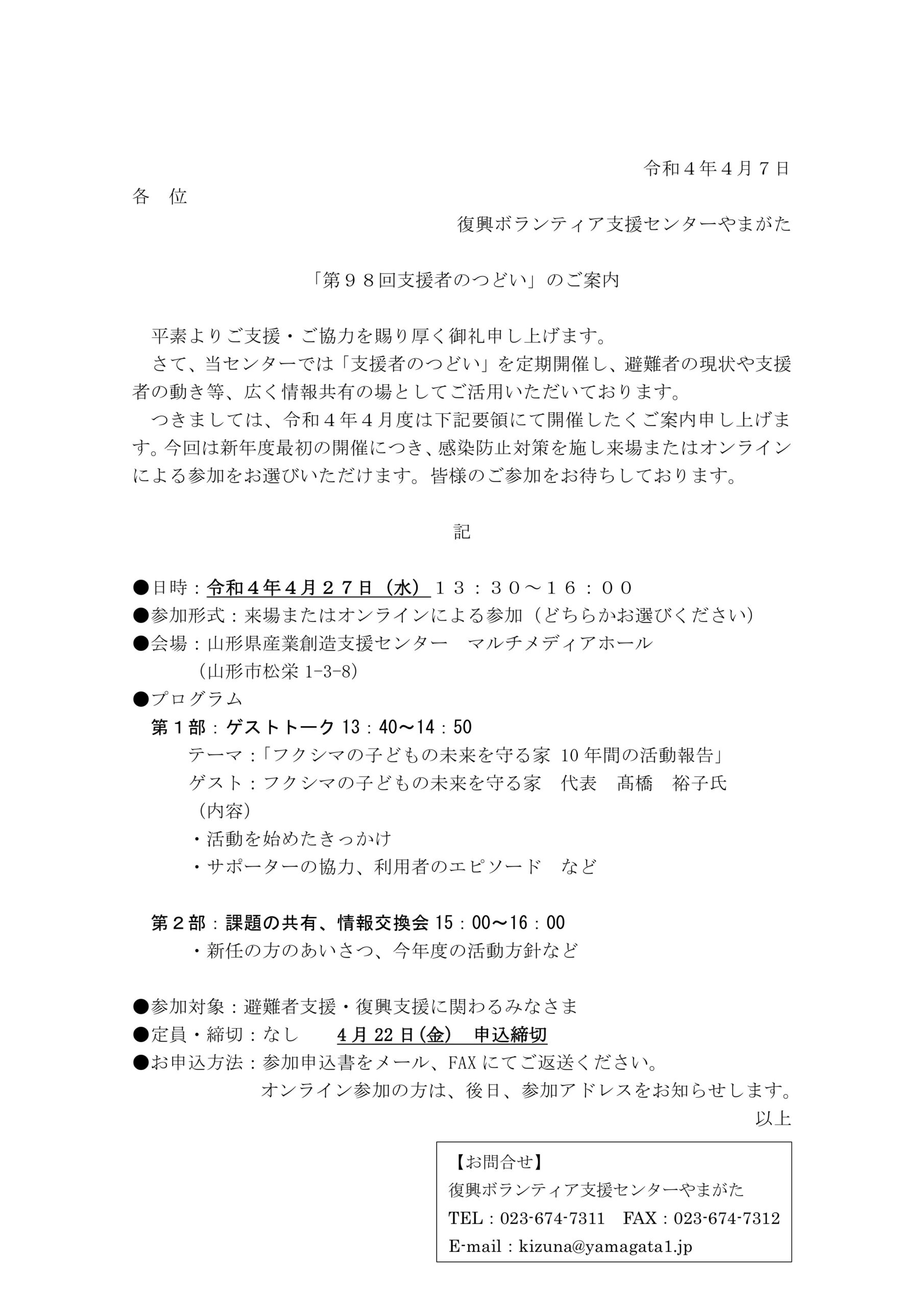平成27年9月30日 山形市男女共同参画センターを会場に 第48回 「支援者のつどい」を開催しました。話題となった概要を広く皆様にお伝えします。
【参加団体】
<民間団体>
カウンセリング 2団体
ボランティア育成 1団体
調査 2団体
中間支援 1団体
情報支援 1団体
<公的団体>
山形県復興・避難者支援室
山形県社会福祉協議会
山形市社会福祉協議会
山形市総務部防災対策課
山形県健康福祉部地域福祉推進課
米沢市避難者支援センター おいで
参加者数:18名(13団体)
<活動報告、課題の共有等>
■県内の支援活動
・ウェルビーイング(主観的健康感)の調査を実施した。8/28 12歳以上の避難者を対象にし、全体で61世帯92名の方から返送された。訪問希望は29名。
・先週、名古屋日本心理学会のシンポジウムの中でウェルビーング氷山モデルや山形市の取組みについて発表した。山形市のデータは今後も分析していく。
・ウェルビーイングは、心の健康度が高いか、低いかを見るもの。人間関係をつくることにも活用したい。低い人には面談を働きかけ、医療機関にもつなげていきたい。一方で、得点が高い人にもなぜ高いかを聞く。今後の支援は心の面だけではないが繋がることが大切。
・相談員のいない地域を訪問した。定住を希望している世帯が多く、福島県の情報は欲しいが訪問活動等の支援はいらないという世帯が多い。避難者数が少ない市町村に住んでいる世帯は、支援がもう必要ないという人が多く、未だに支援をしてもらっているという目で見られるのが嫌だという話も聞かれる。仕事に就いている人も多く、経済的な心配はいらないという世帯も多いが、一方で支援者からは生活困窮世帯が増えているという情報もある。
・10月30日に避難者支援ネットワークの県全体の意見交換会議を開催する。福島県の住宅支援終了後の支援については年末に向けて検討している。山形県では避難者にアンケート調査を実施した。
・昨年度に引き続き県のストレスケア事業を受託し、子供向け・大人向けのセラピーを行う。リピーターが多く、子どもの教室が定員に達した。大人向けはグループセッションはまだ余裕がある。
・イベントに来ているのは、活動的な人が多いが、自己肯定感が低く、一見すると明るいが個別に話をすると泣き出すような人もいる。子どもが色々な問題を抱えていることも多く、元々の要因である人が多い。避難者には有償でイベントの手伝いをお願いすることもある。
・最近は、カウンセリングと同時にコーチングのような話を求められることが多くなってきた。
・H29年3月の借り上げ住宅終了後についてどう考えているか、聞き取りをしている。子どもがいる人は子どものことを一番に考え、卒業など子どもの進路に合わせて今後のことを決める人が多い。地元の家族から帰ってこいと言われることが増えたという話がある。借り上げ終了後の支援について、不安を持っている人も多い。
・毎月1回の「花はな会」では、自分達で公民館を借りて手芸の続きをやりたいという前向きな話がでた。
・母親たちの環境は変わってきている。避難してからの悩みと、震災前からの問題を震災とダブらせていることが分かれてきつつあるように感じる。
・夫婦間で温度差が生まれている。母親は震災時より気持ちが変わっていないが、父親は中通りで普通の生活を送っている同僚や友人に、避難していると言えないという声がある。
・おいでは12月にクリスマス会を行う。スタッフ含め200名を想定。
・JPFの補助を受け、避難者支援団体の活動内容を紹介するページを作成している。6団体の記事を掲載した。
・在宅ワークのパソコン教室を行っている。パソコンは高齢者も興味がある。企画があれば声をかけてほしい。
・山形県の社会貢献基金で4回の災害ボランティア研修を予定している。第1回は10月18日。
■県外の支援
・戸塚区や青葉区にも避難者が集まる場所がある。鎌倉市にも避難者の集う場や、保養支援を行っている人もいる。
・そもそもの問題を抱えた上で避難している人が多く、それに起因した問題が発生しているようで、継続して相談を受けることが多い。生活困窮者も増えているし、福島だけでなく関東でも癌患者が増えているという話も聞く。
・仙台でフルブライトシンポジウム「地域・自然・人間の関わり」が開催された。CWニコル氏、他4人のパネリスト(ジャーナリスト、Earth Angels代表、希望の牧場代表)がそれぞれの視点から、福島との関わりについて話をした。
・東京の市民科学会議のシンポジウムで印象に残ったのは「リスクの概念について」。リスクの話は専門家ではなく民衆の話であり、どのくらい被ばくさせても良いのかについても、国が話合うのではなく民衆が話合うこと。
■宮城県栗原市 水害支援状況
・栗原市は大崎市や大和町と同じ規模、床上が172棟100世帯、床下が270世帯。
・今回は社協でボランティアセンターを立ち上げていない。聞きつけたボランティアが、全国から集まっている状況。
・地元の寺を「地域支え合い拠点」のようなかたちで運営して行けたら良いと考えている。お寺の拠点で活動している人達と栗原市社協が、ニーズや参加者の名簿やボランティア保険についても共有する。
・現在栗原市は、対策本部を閉めて消石灰や物資の支援も打ち切っている。
以上