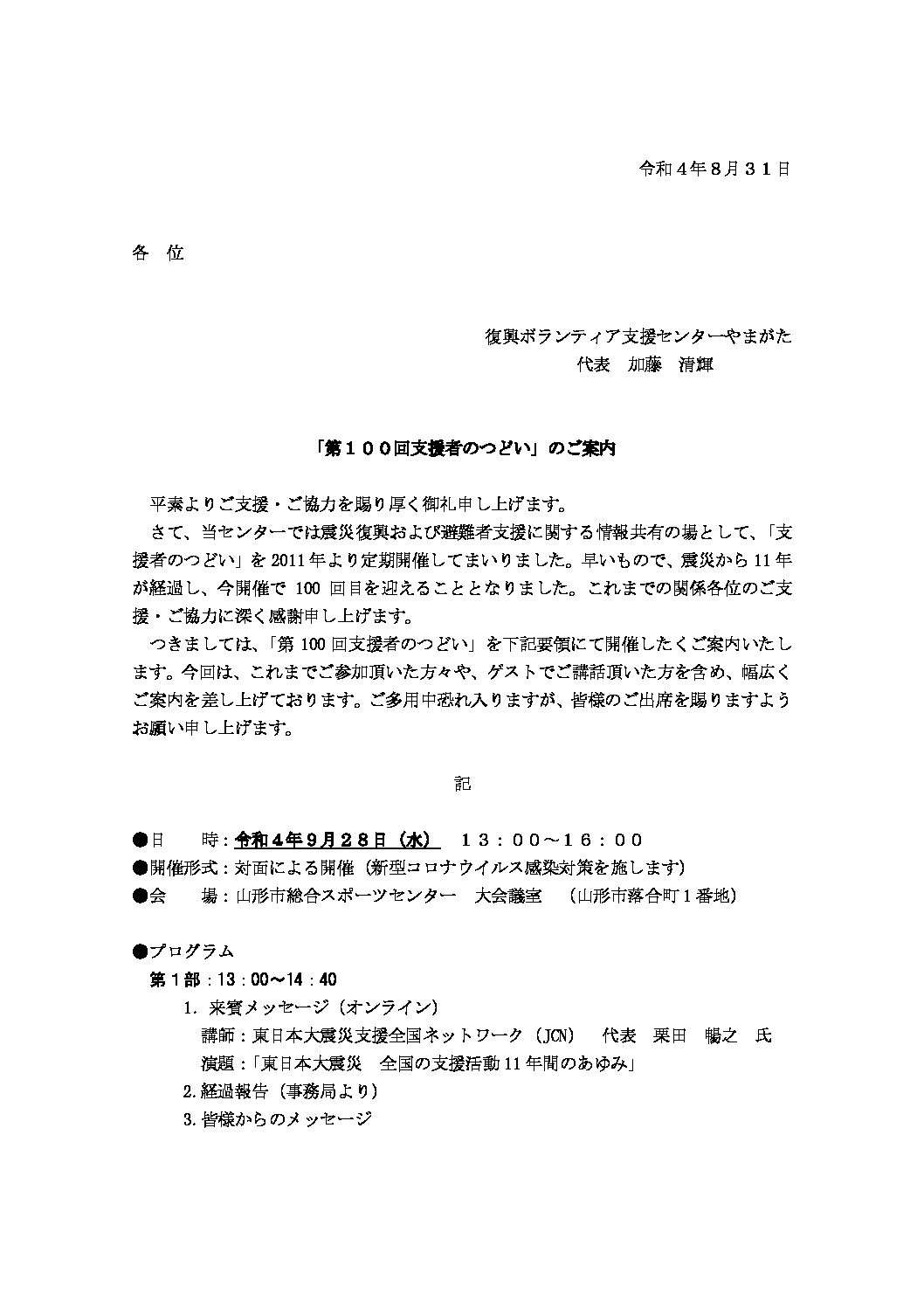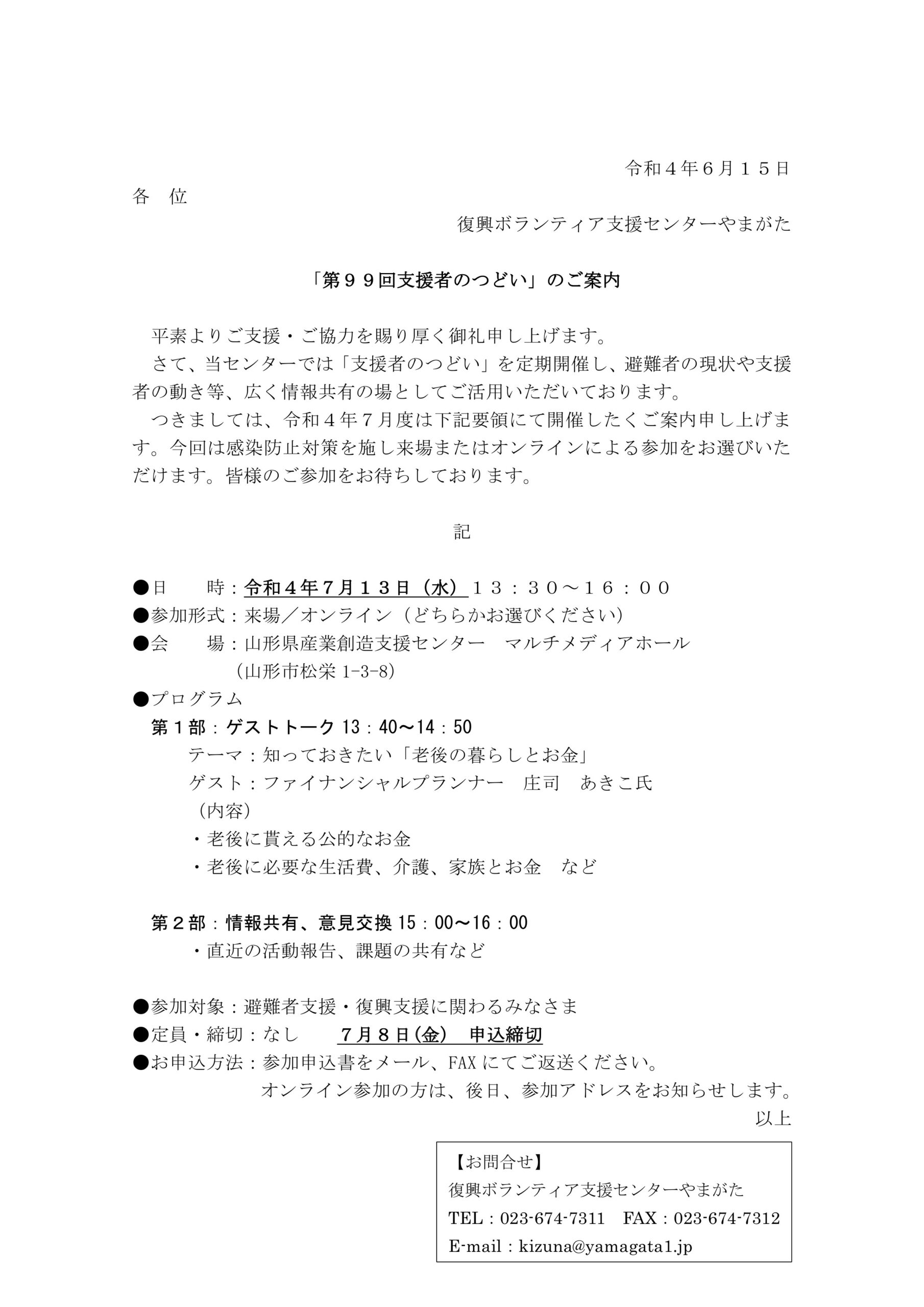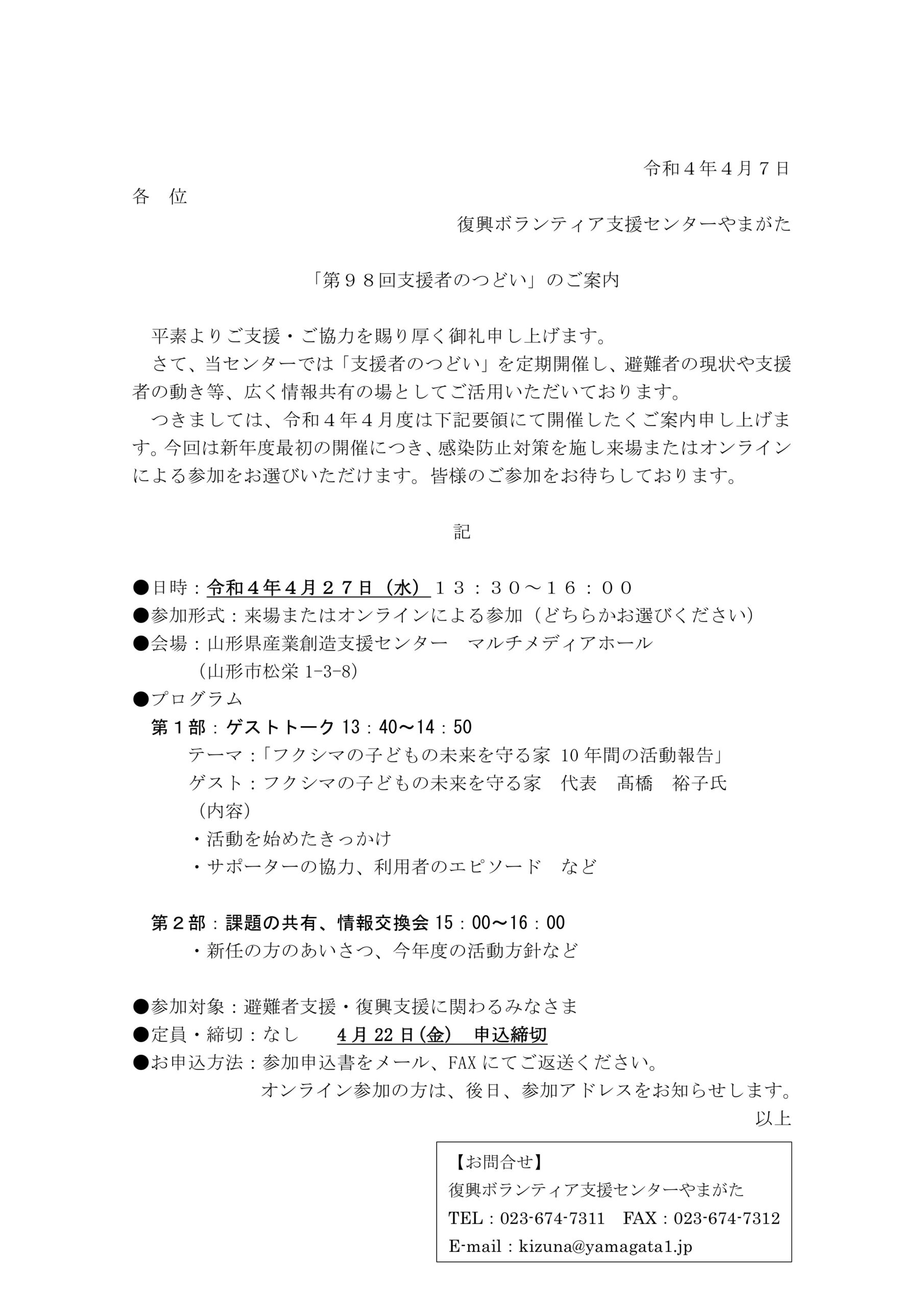平成28年2月24日、山形市男女共同参画センターを会場に、第52回 「支援者のつどい」を開催しました。話題となった概要を広く皆様にお伝えします。
※今回は内容が多いため、第1部と第2部に分けて掲載します。
[第2部]
■情報交換(活動報告、課題の共有等)
<コミュニティ支援・学習支援>
・避難者世帯150→30世帯に。避難者の数も減り、働く人も増え、サロン参加者も減少し、どのようなかたちでサロンをしていけば良いのか悩んでいる。
・サロンへの補助も年々減っているため、参加者の自己負担も増えている。
・避難者は集まる場所を楽しみにしていて、情報交換や癒しの場になっていると感じる。
・訪問しても会えない世帯が多くなってきた。子どもが大きくなり活動範囲も広くなって、働き始めたのではないかと思っている。母子には母子なりの悩みがあり、どこで話をしたらよいか悩んでいるのではないかと心配している。
・働く人が増え、自立に繋がっている反面、イベントを開催しても来てもらえない。土日に開催するようになったが、平日開催は年齢に関わらず人が来てくれるのはないか。
・帰還、定住、悩んでいる方の個別支援が、今後の課題だと考えている。
・「まちの保健室」、「ふくしま就職相談会」、「浜通り交流会」は今後も継続する。
・2013年から避難者を対象に月1回の学習支援活動をしている。
・表立って避難者だと言いたくない人もいて、一般の人も対象にした後から参加するようになった避難者もいる。
・花はな会に洋服の支援をいただき感謝している。
・「何かをやってもらう」「施される」という段階を超えていて、昨年・今年はスタッフとして手伝うことに喜びを感じている避難者もいる。
・何かをやってもらうばかりでなく、スキルを身に着けて周囲の人に恩返しをしたいというニーズは高い。
・サロン参加者が減っているという話があったが、自分達だけで考えると煮詰まってしまうので、実際の避難者の話を聞いて決めたほうが良いのではないか。
・避難している母親たちの団体と活動を続けている。常設サロンはある程度固定化された避難者が集まり、自分たちの居場所であり、深い話を語り合える場になっている。集まる場所を継続させるのは重要なこと。
・働いている母親のため、昨年の9月から夕食会もしている。
<心の支援>
・アートセラピーの大人向け・子ども向けのイベントをしている。最近は子どものことや母親自身のことなど細かい相談が増えた。
・今までイベントに参加していなかった人が、友人に誘われて来たことをきっかけに、カウンセリングなどで心を開いて、他のイベントにも参加するようになったということもあるようだ。
・震災前から社会の中で問題を抱えた大人たちや生きづらさを抱えている人への相談支援をずっとしてきた中で、話を聞くと矛盾をたくさん抱えた幼少期を送っていることが多い。例えば、ひとつの物事に対して父・母の言うことが違うなど、「ダブルマインド」があると、思春期に自分で決められなかったり、反抗するようになり、大人になっても矛盾として現れる。心の復興は家庭からだと感じる。
・心理療法士を県から派遣してもらい、カウンセリングを実施。子どものいじめ、離婚の悩み等、今まで5回相談があった。帰還者が増えている中、避難を続けている人の悩みは深くなっていて申込みが増えている。来年度も考えていきたい。
<イベント・告知>
・福島県に戻る人向けに2回目の就労支援セミナーを行う。
・3月は、お弁当を食べるランチ会を行う。
・3月11日の復興祈念事業はセレモニーや山形交響楽団の演奏、キャンドルの点灯等が行われる。
・3月11日14:40~千年和鐘前で式典がある。
・3月11日に米沢市で「復興のつどい・追悼式」を行う。
・3月12日に森の休日スタッフ研修会を行う。福島の家族もゲストで来てもらう。
・ふるさと福島帰還支援事業は拡充しながら実施。3月中旬に募集を開始する予定。
・月1回、避難者を対象にパソコン講座をしている。
<制度について>
・借上げ終了後の福島県の新しい支援策が間違って伝わっていることがあるので、正しい情報を伝えていきたい。
・自主避難者の借上げ終了後にどうするか迷っている方も多いが、寄り添った支援をしていきたい。
・借上げ終了発表以降、具体的な決断のための情報交換は現実的なものが多い。
・福島県に戻ってからの住み替えは制度的に難しく、わかりにくい。避難指示区域以外の子どもがいる世帯は福島県に戻る際に住み替えが可能。
・H29年3月末までの高速道路の無料措置延長が発表になった。
・制度支援はどこかに限界があるもの。制度からはみ出た部分を民間が連携して、受け皿になっていければいいと思う。
<県外支援>
・2011年から「シネマエール東北」という岩手・宮城・福島に映画を届けるプロジェクトに参加。福島県と宮城県の一部に行っている。最初は避難所から始まり、仮設住宅になり、今は一部復興公営住宅で新しいコミュニティの支援として上映をしている。
・昨年まで仮設校舎にいた伊達市の梁川小学校で毎年上映会をしている。今後は映画上映だけでは難しいため、他団体と連携して、映画を通して何か展開をしたいと考えている。
・福島の小学校の校長先生が生徒を山形に連れていきたいという話をしていた。実行するためには人手もお金もかかる。お知恵を貸してくれる方がいたら協力をお願いしたい。
<保養について>
・2012年より週末保養「森の休日」を45回続けてきた。来年度は4~7月に開催予定で、募金が集まれば秋も開催できる。募金する人は減っているがリピーターが多い。
・週末保養を継続するのは金銭的にも人員的にも困難だと感じている。
・自宅の離れをリフォームした。一軒家を家族単位の保養に使ってほしいと考えて準備している。
・山形市内で自由に宿泊できる場所の需要は高いと感じる。
・山形市中心部にある浄土真宗のお寺内の和室で土・日に「週末Stay@やまがたのお寺」をしている。ニーズは途切れることが無く、昨年は100人以上の家族が利用した。和室2間に1~2家族が宿泊しているので予約希望が重なり、断ることも多い。金の夜から利用できる。来てくれた人の感想を見ると、「もう少し頑張ろう」と思い、継続できている。
<その他>
・避難者数は2月4日現在3,500人以上の避難者、うち9割は福島県からの避難者。
・28年度の取組みとして、相談会や情報提供を考えている。定住者向けの情報提供がこれまで十分に行われていなかった。悩んでいる人向けに選択肢としての情報をなるべく多く持ってもらいたい。
・福島に戻ったからそこで終わりではなく、悩みもあるのではないか。
・一般の転入者扱いで帰る人もいれば、避難から戻った人として迎えられる場合もある。福島に帰ってからの見守りや情報提供に差が出るのではないか。支援が必要な人に対しては、橋渡しをする必要があるのではないか。
・HPで情報発信をしている。見る人が固定化している中、色々な人に情報をどう届けるかが課題。
以上